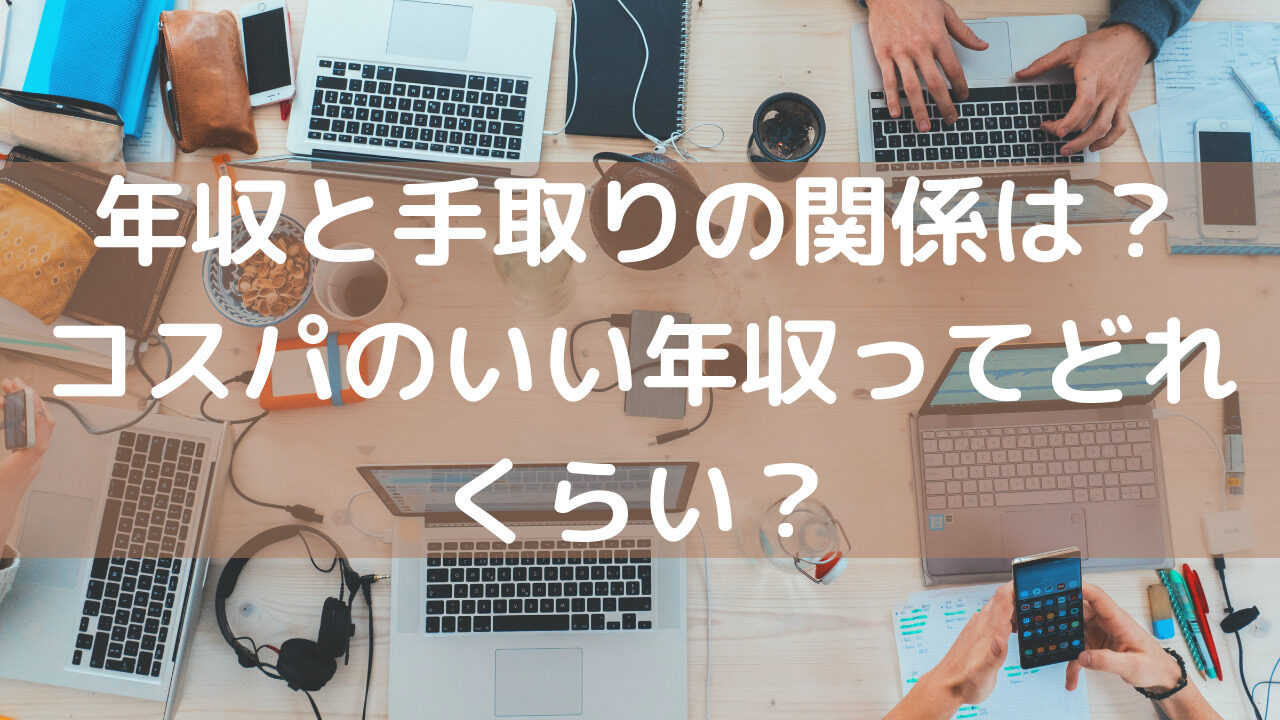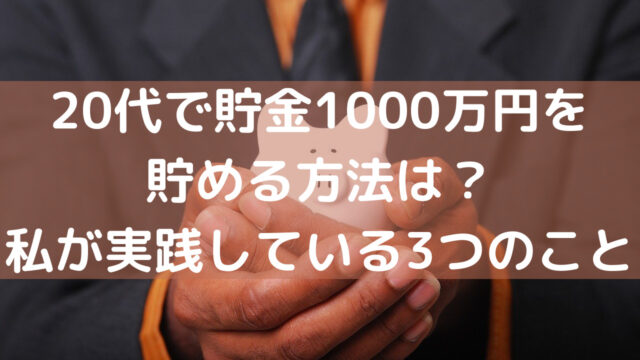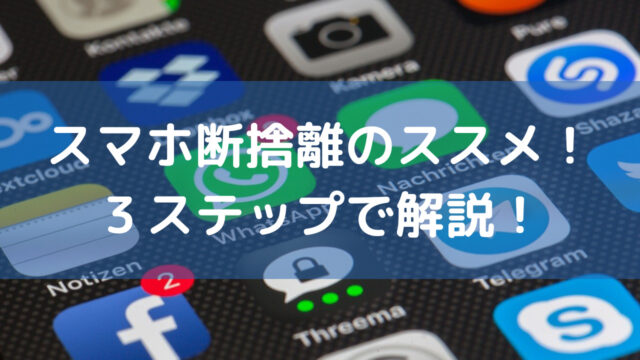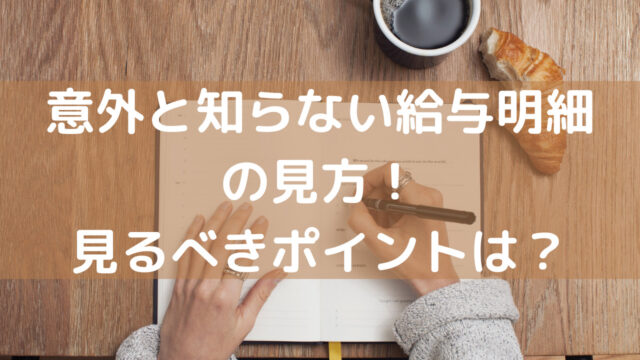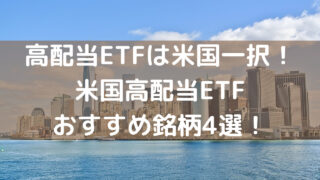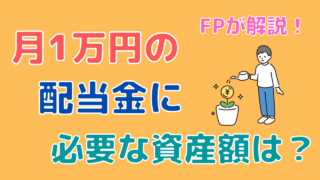こんにちは、FPブロガーのムツヲです。
自分の年収や手取りが気になることってありますよね。
「自分の年収はいくらなんだろう?」
「給料が上がったら手取りはどれくらい増えるんだろう?」
もちろん給料が増えれば基本的にはそれだけ手取り額も増えますが、その分税金などの負担も大きくなります。
この記事では、そんな年収と手取りの関係やコスパのいい年収についても解説します。
・年収と手取りの関係
・年収アップによるメリット・デメリット
・コスパのいい年収とは
年収と手取りの関係

ご存じの方も多いと思いますが、年収とは毎月の給与明細の「総支給額」に書かれた金額の合計です。
いわゆる「年収~万円」というときはこの金額を指します。
対して、手取りとは毎月の総支給額から税金や社会保険料が引かれて「手元に残った額」の合計です。
つまり、基本的に年収>手取りになります。
ここでは、年収別に手取り金額がどれくらいになるかを解説します。
年収と手取りの早見表
普通に考えると年収が上がればそれだけ手取りも増えるはずですが、税金や社会保険料は年収の多い人ほど多く支払うことになります。
そのため、年収が上がるほど手取りの増加率は下がっていきます。
以下でその関係を表で示します。
実際の年収と手取りの関係は、年齢・家族構成・経済状況・節税対策などで変化しますが、今回は独身のサラリーマンで考えます。
| 年収 | 手取り | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り割合(%) |
| 300 | 240 | 42 | 6 | 12 | 80 |
| 400 | 317 | 57 | 8 | 18 | 79 |
| 500 | 390 | 71 | 14 | 25 | 78 |
| 600 | 463 | 85 | 21 | 31 | 77 |
| 700 | 531 | 99 | 32 | 38 | 76 |
| 800 | 594 | 114 | 47 | 55 | 74 |
| 900 | 657 | 128 | 62 | 53 | 73 |
| 1000 | 720 | 142 | 77 | 61 | 72 |
このように年収が上がるごとに年収に対しての手取り額の割合は下がっていきます。
皆さんはこの表に当てはめるとどれくらい手取りがもらえそうでしょうか。
年収が上がるほど多くのお金を国や自治体に支払うことになるため、うれしくもあり悲しくもあるといった感じですよね。
ただ、これはあくまで何も対策をしなかった場合の試算額なので、各種控除や節税を行うことで手取り額を増やすことは可能です。
サラリーマンでもできる「iDeCo」や「医療費控除」などについては以下の記事で解説しています。
年収アップによるメリット・デメリット

年収が上がることはいいことしかないと思われがちですが、実は年収アップには良い面と悪い面があります。
ここでは、そんな年収アップのメリット・デメリットについて解説します。
年収が高いことによるメリット
その①手取り額が増える
当たり前ですが、基本的に年収が上がれば上がるほど手取り額が増えます。
自由に使えるお金が増えることは年収が高いことの最大のメリットです。
効率などを考えずにただただ手取りが多ければいいという方は、このメリットだけで十分かもしれません。
その②より大きな金額のローンが組める
高年収はお金を借りる点でも有利になります。
住宅ローンや投資ローンを組むときにより低い金利でより大きな金額を借りることができます。
例えば、年収が低いと金利が2%のところが年収が高いと1%で借りることができます。
また、年収が低いと2000万円しか借りることができないが、年収が高いと1億円借りることができる場合もあります。
①手取り額が増える
②ローンが有利になる
年収が高いことのデメリット
その①年収に対する手取り額の割合が下がる
上の表でもわかるように年収が上がるほど手取りで残る割合は下がります。
それは年収が上がるほど
⑴所得税率が上がる
⑵給与所得控除の割合が下がる
という2点が生じるためです。
税金は(収入-控除)×税率で計算されるため、税率が上がるほど税金が高くなり、控除が下がるほど税金が高くなります。
「所得税率」は所得金額に応じて5%~45%の間で変わるため、年収が高い人ほど税率が高くなるようになっています。
所得税や年収と所得の関係については詳しくこちらで解説しているので、
「???」という方はまずはこちらをチェックしてみてください。
また、「給与所得控除」も年収に応じて計算式が変わるため、年収が高い人ほど給与所得控除で引くことのできる割合が下がります。
その②各種控除が使えなくなる
年収が一定額を超えると様々な控除が下がったり、使えなくなります。
具体的には、
⑴配偶者控除が下がる
⑵基礎控除がなくなる
⑶住宅ローン控除が使えなくなる
という3つの控除が下がるもしくは使えなくなります。
「配偶者控除」は、年間所得が900万円以下だと38万円の控除がありますが、
900万円を超えると26万円、13万円と段階的に下がり、所得が1000万円を超えると0円になってしまいます。
「基礎控除」は、年間所得が2400万円以下の人は誰でも48万円の控除が受けられる制度ですが、
2400万円を超えると段階的に下がり、2500万円を超えると0円になってしまいます。
「住宅ローン控除」は、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間控除できますが、
年間所得が3000万円を超えると住宅ローン控除を使えなくなります。
このように年収が増えると各種控除が下がる・使えなくなることで税金の負担が重くなる可能性があります。
その③各種手当や給付金がもらえなくなる
年収が一定額を超えると各種手当や給付金がもらえなくなります。
具体的には、
⑴児童手当がなくなる
⑵公的支援が薄くなる
という2点があります。
「児童手当」は、子供が中学卒業するまでの15年間で1人当たり約200万円支給されますが、
2022年10月からは年収が1200万円を超えると支給されなくなります。
「公的支援」は、住宅購入の際の「住まい給付金」や教育費負担減のための「高等学校等就学支援金制度」などが少なくなってしまいます。
①税率が上がる
②控除が下がる、使えなくなる
③手当や給付金ががもらえない
高年収にはこのようなデメリットもあるため、がむしゃらに稼ぐのが吉とは言えないかもしれません。
コスパのいい年収とは

年収と手取りの関係や高年収のメリット・デメリットについて解説しました。
ここではその内容を踏まえて、コスパのいい年収はどれくらいなのかについて解説します。
コスパのいい年収の要素
記事の内容を踏まえ、以下の要素に当てはまるものをコスパのいい年収としました。
・税率が低い
・各種控除や優遇制度が受けられる
・日常生活や老後資金に困らない
記事の内容を踏まえたまさにコスパのいい年収の要素と言えるのではないでしょうか。
コスパのいい年収
上の要素から考えられるコスパのいい年収は「約600万円(手取り約460万円)」です。
年収から控除額を引いた所得は約300万円になります。
所得(300万円)=年収(600万円)-各種控除(300万円)
所得が300万円の場合は、所得税率は2番目に低い10%になります。
また、各種控除や手当もほとんど利用することができます。
手取り460万円ほどあれば生活費を年間300万円、旅行などの特別支出を60万円としても、100万円を投資や貯蓄に回すことができます。
仮に貯蓄30万円、70万円を年率5%で運用すれば20年後には2000万円を超える金額を保有することができます。
このように老後資金の準備にも困る可能性は低いです。
つまり、年収600万円は税負担が重くなく、各種控除や手当が使えて日常生活や老後も困らないコスパのいい年収と言えます。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の記事はサラリーマンとして給与をもらっている方は特に気になる内容だったかと思います。
給与は自分で決めるのが難しいため、節税対策によって自身で手取り額を増やす努力が必要です。
サラリーマンにもできる節税対策の記事はこちらです。
【節税も⁉】iDeCo(イデコ)とは?わかりやすく解説しました!
【FP解説】ふるさと納税とは?お得な制度の仕組みを解説します!
【FP解説】医療費控除とは?いくら節税できる?制度概要と節税の仕組み
【会社員必見】意外と知らない給与明細の見方!見るべきポイントとは?